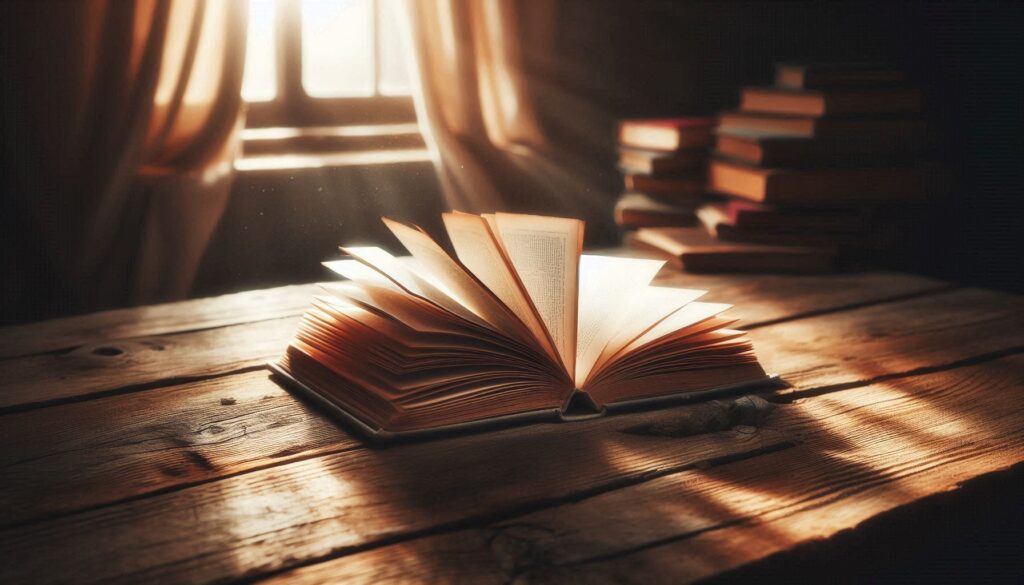
「静岡駅の改札を出た時、まさか自分が4時間の地獄を見ることになるとは、1ミリも想像していなかった。」
お茶の香りが漂う穏やかな街、静岡。旅の締めくくりに「さわやか」のハンバーグを食べて帰る。それは、ありふれた、あまりに幸福な計画のはずだった。しかし、セノバ9階で手にした1枚の整理券が、平穏な日常を「新幹線までのカウントダウン」という名の修羅場へと一変させる。これは、肉の聖地で、孤独な戦士が挑んだ1.4万秒の死闘の記録である。
第1章:静岡駅に降り立った「楽観」
新幹線を降りた瞬間、肺を満たしたのは、かすかな茶葉の香りと、地方都市特有の抑制された静寂だった。
旅行、あるいは出張。目的が何であれ、その終焉は常に名残惜しさを伴う。改札を抜けた僕は、自らの内側に芽生えたささやかな欲望を肯定することにした。 「せっかくだ、さわやかを食べて帰ろう」 それは、午後の光の中で思いつくにはあまりに無害で、善良な計画に思えた。
駅前の空気はどこまでも穏やかだ。歩道を行き交う人々は、東京のような性急さを持たず、街全体が深い呼吸をしているかのようにさえ感じられる。僕はそのリズムに身を任せ、新静岡セノバへと足を向けた。
エレベーターに乗り込み、9階のボタンを押す。指先に伝わる冷たいプラスチックの感触。上昇する加速感とともに、僕の期待感もまた、物理的な法則に従って高まっていく。
だが、この時、僕はまだ気づいていなかった。 鋼鉄の箱が最上階に到達し、扉が開いたその瞬間から、僕の知る平和な静岡は姿を消し、そこは「肉」という名の神を求める信徒たちが集う、修羅の地へと変貌することを。
第2章:絶望の「三桁待ち」
チリ、と微かな音を立てて発券機から吐き出された一枚の紙。 それを受け取った僕の視界が、一瞬、白く明滅した。
「240分待ち」
無機質な感熱紙に刻まれた数字は、もはや時間の概念を失っていた。4時間。それは映画を二本観終えてもまだ余り、東京から新大阪を往復してもお釣りが来るほどの空白だ。
左手首の時計に目を落とす。現在は15時。新幹線の発車時刻は19時過ぎ。 「まだ、間に合う」 脳内にある計算機が弾き出した答えは、当初、肯定的なものだった。しかし、思考の解像度を上げると、その楽観は瞬く間に砂の城のように崩れ去る。
店内に案内されるのが19時だとして、そこから注文し、肉が供されるまでの「提供待ち」。鉄板の上で肉塊が完成するまでの儀式的な時間。そして、そこから駅まで全力で疾走する移動距離。 計算式にそれらの変数を組み込んだ瞬間、数字は一気に牙を剥いた。
背筋を、冷たい一筋の汗が伝い落ちる。 新幹線のチケットは、変更のきかない早割だ。もし、1分でも遅れれば、この高価な紙切れはただのゴミと化す。かといって、ここで整理券を捨てれば、僕は「さわやか」という静岡の至宝を、自らの手で葬ることになる。
15時2分。 セノバ9階、喧騒の渦中で、僕はひとり、静かな戦慄に震えていた。これはもはや食事ではない。一分一秒を切り売りする、極限のギャンブルだ。
第3章:セノバという名の迷宮(ダンジョン)
手元の整理券は、今や呪物のような重みを帯びていた。 僕はセノバという名の巨大な垂直迷宮を彷徨い始める。駿府城公園まで足を伸ばし、徳川家康の銅像と対話して時間を稼ぐか、それとも地下の食料品売り場で「こっこ」や「安倍川もち」という名の救援物資を漁るべきか。
思考は千々に乱れるが、最大の敵は「見えない時間の摩耗」だった。 ふとスマホの画面に目を落とすと、バッテリー残量は刻一刻と、砂時計の砂のように削り取られている。LINEの呼び出し通知——それはこの迷宮からの脱出を許可する唯一の福音だが、一向に画面を震わせる気配はない。
ふと周りを見渡せば、そこには同じ「聖痕(整理券)」を握りしめたライバルたちが潜んでいた。ベンチに座り、虚空を見つめる若者。苛立ちを隠せず何度も公式HPを確認する中年。彼らの眼光は、獲物を待つ獣のそれだ。 「皆、同じ地獄を共有している」 奇妙な連帯感と、同時に、一歩でも先に席を勝ち取らねばならないという、生存本能に近い焦燥が胸を焼いた。
第4章:逆転のタクシー、あるいは忍耐の選択
17時。空白だったはずの時間は、残酷なまでに無意味な消費を強いてくる。 ここで一つの選択肢が脳裏をよぎる。 「タクシーを飛ばして、郊外のロードサイド店へ向かうべきか?」
公式サイトが示す、各店舗の待ち状況という名の「戦況図」をリロードし続ける。指先はわずかに震えている。郊外店なら、あるいはもっと早いかもしれない。だが、そこまでの往復時間を考慮すれば、それは破滅へのショートカットになる危険性を孕んでいる。
「いや、動くな。信じて待て」 僕は自らの内なる策士の声に従った。 ここで必要なのは、感情ではない。論理的な**「逆算戦略」**だ。 19時7分の「ひかり」に乗るためには、遅くとも18時50分にはホームにいなければならない。逆算すれば、店を出る限界点は18時35分。提供に15分かかるとすれば、18時20分には着席していなければ、詰み(チェックメイト)だ。
現在、呼び出し番号は僕の15番前を指している。 スマホの画面をタップする力が強まる。これはもはや、ハンバーグを待つ時間ではない。自分の人生における「決断の正しさ」を証明するための、冷徹なシミュレーションだ。 僕は深呼吸をし、セノバの吹き抜けを見上げた。運命の天秤は、まだ激しく揺れている。
第5章:肉塊の儀式、そして疾走
「番号でお呼びの方、お待たせいたしました」
18時16分。ついに宣告(コール)はなされた。限界点まで残り19分。
席に着くや否や、僕は迷わず「げんこつハンバーグ」を注文する。店内に満ちる芳醇な脂の香りが、飢餓状態の胃壁を暴力的に愛撫した。
やがて、運命の肉塊が運ばれてくる。
250グラムの赤身肉。それは生命の輝きそのものだった。店員のナイフが躊躇なくその中心を切り裂くと、断面から溢れ出した肉汁が、華氏482度(250℃)の鉄板の上で狂おしく跳ねる。
「ジューッ――」
鼓膜を震わせる爆音。オニオンソースが接触した瞬間、沸騰した水分が蒸気となって舞い上がり、僕の視界を白く染めた。海堂尊ならこう記述しただろう。「それは毛細血管を駆け巡るアドレナリンと、鉄分を含んだ蒸気の共鳴である」と。
一口。
咀嚼した瞬間、牛肉の弾力と甘みが脳幹を直撃した。至福。だが、陶酔に浸る時間は1秒たりとも残されていない。
僕は時計を見ない。見れば「焦燥」という名の毒が、この「至福」の味を損なうからだ。ただ、身体感覚だけを研ぎ澄ませ、食道へと肉を送り込む。
最後の一口を飲み込んだ。
18時34分。
伝票を掴み、レジへ。支払いは一瞬。店を出た瞬間、肺いっぱいに夜の静岡の空気を吸い込み、僕は地を蹴った。
セノバの階段を駆け降り、駅への最短ルートを脳内ナビゲーションで描く。心臓の鼓動が、アスファルトを叩く足音と同期する。
改札を抜け、エスカレーターを駆け上がる。
プラットホーム。
滑り込んできた「ひかり」の白い車体が、僕の瞳に映った。
間に合った。
座席に深く身を沈め、窓の外を流れる静岡の夜景を眺める。口の中に残る、微かなオニオンソースの余韻。
それは、4時間に及ぶ死闘を戦い抜いた者だけが味わえる、勝利の味だった。